何度も読んだ漂流小説
僕は小さい頃からとにかく自信がありませんでした。ドラえもんに出てくるのび太のように幼稚園の頃からよくいじめられるし、先生には「ウルスくんは落ち着きがない!!」と怒られるし、そのたび泣き叫ぶ毎日。そんな泣いている姿を見て「男らしくない!」という周りからの言葉にどうすればいいかわかりませんでした。
小学生になっても状況は変わらず、スクールカーストでは「中の下」というポジションから抜け出せず、結局高校卒業までそのポジションは抜け出せませんでした。いわゆる「陰キャ」と呼ばれるポジションです。成績も「中の上」から上にいけず、ガムシャラに勉強したとしても頭には入ってこないので成績も伸びませんでした。
この頃はそんな日常から逃げたいと思い、とにかく冒険小説ばかり読んでいました。
特に今回紹介する3冊は何度も読み返していました。航海中に大海原で遭難して、島にたどり着いて衣食住、すべて自分でなんとかして生き残ろうとするバイタリティに元気や勇気をもらっていました。
十五少年漂流記
「海底二万里」の著者で有名なジュール・ヴェルヌが書いた冒険小説で、あることがキッカケで無人島に漂着した少年たちが力を合わせて生き残っていく姿が描かれています。
冒頭の嵐のシーンから島での生活、十五人で協力しなければいけないのに誰がリーダーになるかで揉めるなど、まるでその場に自分がいるような錯覚に陥りそうになります。
小学生の頃は毎年一回、必ず読むくらい好きな小説でした。低学年のころは主人公の活躍に目がいっていましたが、学年が上がるとともに他のキャラクターに感情移入したり、島の情景がより鮮明に想像出来るようになりました。
無人島に生きる十六人
この本は明治時代に起こった実話を元に書かれた作品です。
初めて読んだ時は1ページ目に描かれてかれている「太平洋の地図」や「島の地図」と本文を行ったり来たりして、頭の中で島の生活を想像し夢中になって読んだのを覚えています。初めて読んだのは中学生のときでした。その時は漂流して無人島で生活していく彼らの挫けない生き方に感動しましたが、大人になって読み返してみると別の発見がありました。
中学生の頃は飲み水や火の確保、見張り櫓や食料調達などの「技術」や「能力」ばかり目に入ってきましたが、大人になってから読んでみると「彼らの考え方」の方に注目するようになりました。
例えば「夜の見張り」の人選です。夜の見張りは通り過ぎる船を見張り、見つけたら全員に知らせる重要な役割です。最初は16人のうち若手メンバーが進んで立候補しますが、年長者がそれを諌めて、夜の見張りは年長者だけの持ち回りになります。
特に彼らが漂流中に決めた取り決め「愉快な生活を心がけること」という考え方に僕も影響を受けました。
漂流
高校生の頃に読んだ吉村昭氏が書いたこの本は、前の二冊よりもより過酷でリアリティの溢れた漂流小説です。
13年もの歳月、無人島で生活し生き残った主人公、長平。漂着した島は火山島で飲水も無く、草木もほとんど生えず、唯一の食料は魚や貝、そして渡り鳥です。
そんな過酷な状況に絶望し、精神的に参って衰弱死していく仲間たち。普通なら心が折れそうになりますが長平は結局生き残り、最後は島を脱出して生まれ故郷に帰ります。
彼が他の漂着者と何が違ったのか? それは彼が生きるために過去を振り返らず(=故郷に帰りたい)、未来に絶望せず(=自分は一生この島から出られないのだ)、ただ黙々と毎日衣食住のために身体を動かし続けたからです。
このパターンは現代にも通じるものがある気がします。過去の出来なかった自分を思い出したり、「老後は大丈夫なのだろうか?」「自分は結婚できるのだろうか?」など自分の未来に対して絶望したりすると人間は簡単に衰弱してしまうんです。
「今」に集中する、そして定期的に身体を動かすことの大切さを学びました。
まとめ
大人になった今でもこの三冊を読み返すと元気がもらえるし、未だに「こんなこと書いてあったんだ!」という気づきがあります。
「もう心が凹みすぎて本を読む元気すらないよ…」という人も最初に紹介した2冊は読めると思います。児童文学なので文字も大きいし、挿絵も多いのでその世界に没頭できるでしょう。きっと彼らから元気がもらえるはずです。

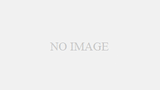
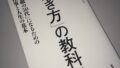
コメント