歴史小説家、塩野七生さんの随筆「逆襲される文明」を読みました。2014年~2017年にかけての世界情勢や社会の移り変わりを塩野さん独自の視点で語られている本です。
この本を読んでいると「民主主義」という政治形態について深く考えさせられます。どういういことかというと学生時代の知識のままで止まっているとこの「民主主義」という政治形態が何やらキレイで美しくて素晴らしいものと考えているからです。
しかしそんなことは無いという現実を見せつけられます。現代のイタリアに住んでいて、また古代ローマ帝国、古代ギリシア世界という民主政の元祖を題材にして小説を書いてきた著者が書いているためか、2つの時間軸の異なる世界を対比することで非常にわかりやすい説明になっています。
現実のヨーロッパは問題が山積みのようです。そしてマスメディアを通してでしか知らない日本人が持つ綺羅びやかなヨーロッパのイメージからはかけ離れたものだというのがわかります。
ではなぜ問題が解決しないのか? それは大衆迎合に陥ってしまった政治は大衆が痛みを伴う政治を実行出来なくなるからです。政治家は選挙に負けたらタダの人です。大衆に嫌われて選挙で落とされることを恐れて大衆に迎合してしまいます。それゆえにヨーロッパ各国のリーダー達はリーダシップが取れず、結局問題は先送り先送りになってしまいました。
ここで私達が学ばなければいけないのは、民主主義というのは私達の生活の延長線上にあるということです。生活の延長線上にあるということはキレイで美しいワケがないんです。どこか泥臭くて、薄汚れているのが普通なんです。
どこか私達は政治というものは公明正大、清廉潔白であらねばならないという想いがある気がします。でも塩野さんが比較する古代ローマ帝国は泥臭い政治を行っているわけです。そしてそこに登場するリーダーたちもどこか人間臭い、清濁併せ呑むタイプが多いのです。
「民主主義なんてどこか薄汚れていて白にはならない」そう考えると「今の生活が悪いのは政治のせいだ!」とか「あの政治家はなんて悪い奴なんだ!」とか思わずに精神衛生上、普段の自分たちの人生を精一杯生きれるようになる気がします。

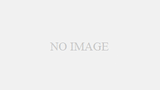

コメント