吉村昭氏が書いた「空白の戦記」を読んだ。
この本を一言で表すなら我々が普段テレビや新聞、Webサイトから知るような不幸なニュースをドキュメンタリー風に知ることが出来る短編集だ。
しかしそのドキュメンタリーの題材は太平洋戦争前、そして戦争中の日本が舞台である。
普段我々が触れる不幸なニュースの数々は多くの場合、一回触れたら次の日には忘れ去られる。思い出したとしても年末に特集される「今年のニュース」でもう一度触れて、「ああ~。そういえばそんなニュースもあったな~」くらいだろう。
そのため、今後この本で触れられる小さな事件が歴史の教科書に載ることは無いだろう。あまりにも小さな事件は歴史の大きな流れを把握する上では意味がないと判断されるからだ。
しかし大きな歴史の流れだけを追ったとしても分からないことがある。それは当時の社会の空気や雰囲気を作る人々の「価値観」だ。
・1941年12月に日本海軍が真珠湾を攻撃し太平洋戦争が始まりました
・1945年8月に日本は降伏しました
といった大きな事件は歴史の教科書で淡々と述べられている。だがこれらの事件の羅列からは当時の人々が持っていた価値観を感じ取ることはできない。それを感じ取るには本書で書かれている様な小さな事件に触れるしかないのだ。
歴史とはモザイク画とも言える。一つ一つのピースを小さくすると写真のような鮮明なモザイク画になるように、歴史も一つ一つの小さな事件を深堀していくと鮮明にわかってくる。
さて今から85年前に日本は終戦を迎えたわけだが、この本から垣間見える当時の人々の価値観には驚かされる。
例えば「敵前逃亡」という作品に出てくる中学生三年生の男子生徒。彼は民間人ながらアメリカの沖縄上陸が近いという事もあり陸軍二等兵として沖縄守備軍に組み入れられる。しかしひょんなことからアメリカ軍に捕まり、そこで米軍からある提案を受ける。投降勧告に協力してくれないかと。彼は表向きそれを受諾するが、内心は投降勧告するふりをして味方陣地に戻り、再度戦おうと決心していたのだ。
この本から感じ取れることは教育やメディアの恐ろしさだ。当時はテレビも無い為、教育機関や新聞が人々の価値観を作る役割を担ってきた。現代と比べると情報を得られるメディアが少なかったため、国民を一方向に扇動することが容易であった。結果中学生といえども兵士として国に殉ずることに何ら疑問を抱かない価値観が作られる。
この本から何を学べるのだろうか。一つは現代においても教育とネットを含むメディアの力を使えば我々大衆は容易に価値観を植え付けられるということだ。
身近なところで言えば「ファッション」である。今年の流行色は2年前に決まっているし、形状トレンドは各ファッションショーで決められる。
そしてZARAはH&Mなどのファストファッションブランドによりファッションショーが作り出したトレンドに沿った服が作られる。
もう一つ私が思うこの本から学べることは、たった80年ほどで社会の価値観は大きく変わってしまったということだ。
戦時中の日本人の価値観は上記で述べた通りである。
では現代の日本人はどうであろうか?現代の中学生、いや大人ですらも突然民間人が兵士になり敵軍と戦うように命令され従うような価値観はもう無いだろう。
少なくとも私はその価値観を持ち合わせていない。
そのまえに召集令状を無視する人間のほうが多そうだ。なにせ裁判員制度のもと召集がかけられる裁判員ですら辞退率は7割近いからだ。
この事実から次の80年でも同じように価値観が大きく変わることは十分ありうると私は考える。
2020年に発生したコロナウイルスの前後でも大きく価値観は変わった。変わったものの一例を上げるとすれば働き方の価値観の変化は最もたるものでる。
リモートワークが推奨され、ハンコ文化は無くなりつつある。今後リモートワークが制限されたり、ハンコ文化が復活したりする可能性は限りなく低い。
歴史は繰り返される。我々の価値観は誰かによって作られ、変容していくものだということを常に考えておかなければならない。

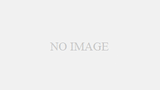

コメント